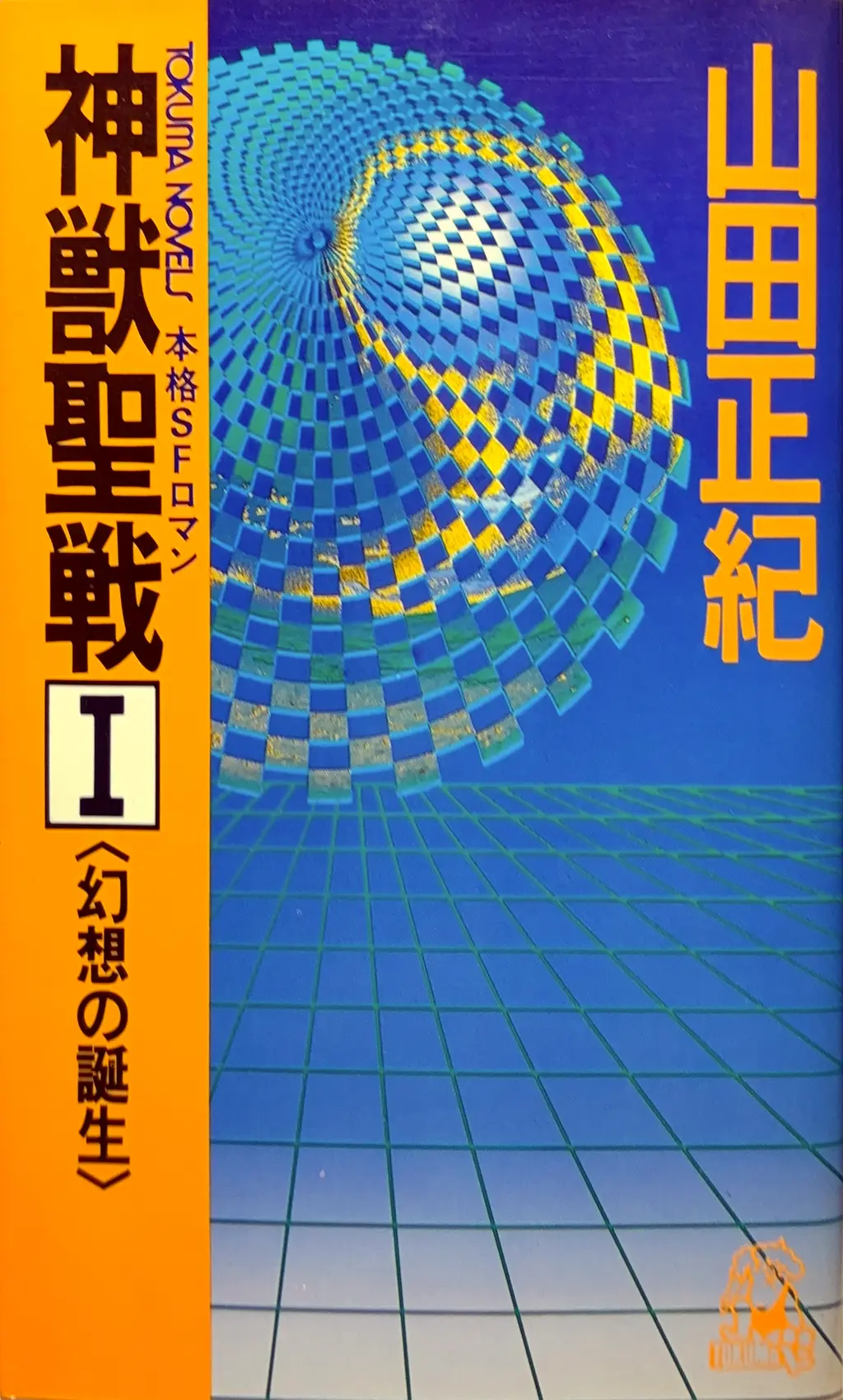| 叢書 | 初版 |
|---|---|
| 出版社 | 徳間書店 |
| 発行日 | 1986/08/31 |
| 装幀 | 生頼範義、矢島高光 |
内容紹介
魔術師:虚実の境界線を溶かす、山田正紀の迷宮世界 ―そして「神獣聖戦」シリーズからの転換―
現実と虚構が交錯する、迷宮的SF小説
物語は、沖縄近海に墜落したB52爆撃機から発見された巨人の死体、米軍脱走兵、幻生代の月、そして“大いなる疲労の告知者”といったSF的な要素が、メタフィクション、RPG、悪夢といった複雑な構造と融合し、読者を混乱と陶酔の迷宮へと誘う。
物語は、SF作家が停電によって執筆中の小説『魔術師』の原稿を失ってしまうところから始まる。必死に記憶を辿り、原稿を復元しようとする作家。しかし、プリンターから出力される物語は、以前のものとは微妙に変化している。まるで物語自体が意思を持っているかのように、作家の意図を逸脱し、新たな展開を見せ始める。
消失と再生、変容する物語
作家の書き進めていた『魔術師』は、米軍脱走兵の水島ら四人が、蘇生した巨人と共にB52爆撃機で幻生代の月へと向かい、“大いなる疲労の告知者”と対峙するという、壮大なスケールのSF冒険譚である。この物語は、RPGのセッションのように進行し、登場人物たちの行動や選択によって、物語が分岐していく。
しかし、停電後の物語は、作家の記憶とは異なり、予期せぬ方向へと進んでいく。登場人物たちは、まるで生きているかのように、作家のコントロールを拒否し、独自の行動を取り始める。現実世界で原稿を復元しようとする作家と、物語世界で独自の運命を辿る登場人物たち。二つの世界は、互いに影響を及ぼし合い、虚実の境界線を曖昧にしていく。
メタフィクション、RPG、悪夢。重層構造が生み出す迷宮
『魔術師』の特徴の一つは、その重層的な構造にある。メタフィクション、RPG、そして悪夢。これらの要素が複雑に絡み合い、読者を迷宮へと誘う。
作家が小説を書くという行為自体が、物語の中心となっているメタフィクション構造。RPGのように進行する物語世界。そして、登場人物たちが体験する悪夢のような出来事。これらの要素が、現実と虚構、内面と外面の境界線を溶かし、読者を混乱の渦へと引きずり込む。
創作の苦悩、記憶の不確かさ。作家の内面世界
『魔術師』は、SF冒険譚であると同時に、創作の苦悩と記憶の不確かさを描いた作品でもある。原稿を失い、記憶を頼りに物語を再構築しようとする作家。しかし、記憶は曖昧で、完全な再現は不可能である。
物語が変容していく過程は、創作活動における試行錯誤や、記憶の不確かさを象徴している。作家は、失われた物語を取り戻そうと苦闘するが、その行為自体が、新たな物語を生み出していく。このプロセスは、創作活動の本質を鋭く捉えていると言えるだろう。
“大いなる疲労の告知者”とは何か?
物語の中核を成す“大いなる疲労の告知者”。その正体は、物語全体を通して謎に包まれている。それは、宇宙的な存在なのか、それとも人間の深層心理に潜むものなのか。様々な解釈が可能であり、読者一人ひとりが、それぞれの“大いなる疲労の告知者”像を構築していくことになる。
この曖昧さが、作品の魅力の一つとなっている。明確な答えを与えず、読者の想像力に委ねることで、物語はより深い意味を持つようになる。
終わりのない物語、無限の可能性
『魔術師』は、明確な結末を持たない。物語は、作家の創作活動と共に、無限に続いていく。この終わりなき物語は、創作の可能性、そして人間の想像力の無限性を示唆している。
読者は、作家の苦悩と希望、そして変容する物語世界を共に体験することで、創造の喜びと苦しみ、そして現実と虚構の狭間にある人間の存在について、深く考えさせられるだろう。
未来史からの脱却、悪夢の探求――「神獣聖戦」シリーズとの関連性
『魔術師』における“未来史”からの脱却、そして悪夢的な世界観への傾倒は、山田正紀の作家としての転換点を示すものと言える。特に、代表作である「神獣聖戦」シリーズとの関連において、この変化は顕著である。
「神獣聖戦III」の後書きで、山田正紀は「自己完結的な未来史に興味がなくなってしまった」と述べている。これは、壮大なスケールで未来世界を描いてきた「神獣聖戦」シリーズのような作品から、より個人的で内面的な世界へと関心が移行したことを示唆している。
一方、『魔術師』の後書きでは、「ようやく悪魔憑きと狂人=鏡人たちの物語を書き継いでいくだけの自信がつきました」と述べている。「悪魔憑き」や「狂人=鏡人」といった言葉は、人間の深層心理や狂気を象徴するものであり、『魔術師』で描かれる悪夢的な世界観と深く関わっている。
これらの発言から推察されるのは、「神獣聖戦」シリーズで築き上げた壮大な未来史という枠組みから脱却し、人間の深層心理や狂気といった、より内面的なテーマを探求したいという欲求が、山田正紀の中にあったということだ。
「自己完結的な未来史」への興味の喪失は、おそらく、未来を予測したり、歴史を体系化したりすることへの限界を感じたことによるものだろう。未来は常に不確定であり、人間の行為によって変化していく。それを固定化された「未来史」として描くことに、山田正紀は陳腐さや欺瞞を感じたのかもしれない。
そして、「悪魔憑きと狂人=鏡人たちの物語」への自信は、人間の深層心理や狂気といったテーマを、より深く掘り下げて描く準備が整ったことを意味している。それは、外側にある未来ではなく、内側にある人間の深淵へと目を向けることで、新たな創作の可能性を見出したということだろう。
『魔術師』は、まさにその転換点に位置する作品と言える。メタフィクション、RPG、悪夢といった要素を駆使することで、人間の深層心理や創作の苦悩といった、内面的なテーマを描き出している。それは、「神獣聖戦」シリーズのような壮大な未来史を描くことから脱却し、新たな境地へと踏み出した山田正紀の、挑戦的な姿勢を示すものと言えるだろう。
読者に問いかける、多層的な読書体験
『魔術師』は、読者に受動的な読書体験ではなく、能動的な解釈と想像力を要求する。重層的な構造、曖昧な表現、そして明確な結末を持たない物語。これらの要素は、読者に独自の解釈と意味の付与を促し、多層的な読書体験を提供する。
『魔術師』は、一度読んだだけでは理解できない、複雑で奥深い作品である。繰り返し読むことで、新たな発見があり、より深い理解へと繋がるだろう。読者は、この迷宮的な物語世界に迷い込み、自分自身の“魔術師”となることで、真の読書体験を得ることができるだろう。
そして22年後、「神獣聖戦 Perfect Edition」へ
そして25年の歳月を経て、再びSFが活況を呈するいま、物語が復活した。著者はかつての連作を劇中劇として組み込み、大枠となる新たな物語を900枚も書き下ろした。日本SFの青春と成熟した現代の文体が作中でぶつかり合う。かつて著者は連作の行方を見失い、すべてを妄想のリアリティーに閉じ込めようとした。当時の著者は作中に登場して弱音を吐こうとさえした。しかし今回の物語は敗北しない。妄想の枠を蹴散(けち)らし、じりじりと異様な迫力を帯び始める。
物語そのものが命を帯びてゆくのだ。80年代と現代の想像力が手に手を取り、著者の弱音さえ吹き飛ばす見事なクライマックスへと向かって進んでゆく。そして最後に世界の運命を定めるのは人間の妄想などではない、一匹の気まぐれな猫だ。長大な物語がついにそこへ集約された瞬間、鳥肌が立ち、熱い涙が溢(あふ)れた。
「怪物の消えた海」「円空大奔走」などかつての短編は紫水晶のようにいまなお美しく、すべてを呑(の)み込む“舞踏会の夜”のイメージも素晴らしい。日本SFの生命力が炸裂(さくれつ)する、山田正紀渾身(こんしん)の傑作だ。
-- 瀬名秀明 2009年1月18日 asahi.comの書評より
さらに16年近くなってこれを書いているわけだけど、全てを俯瞰して見つめ直せる幸せ。また、読み直そう。
 不安と月
不安と月 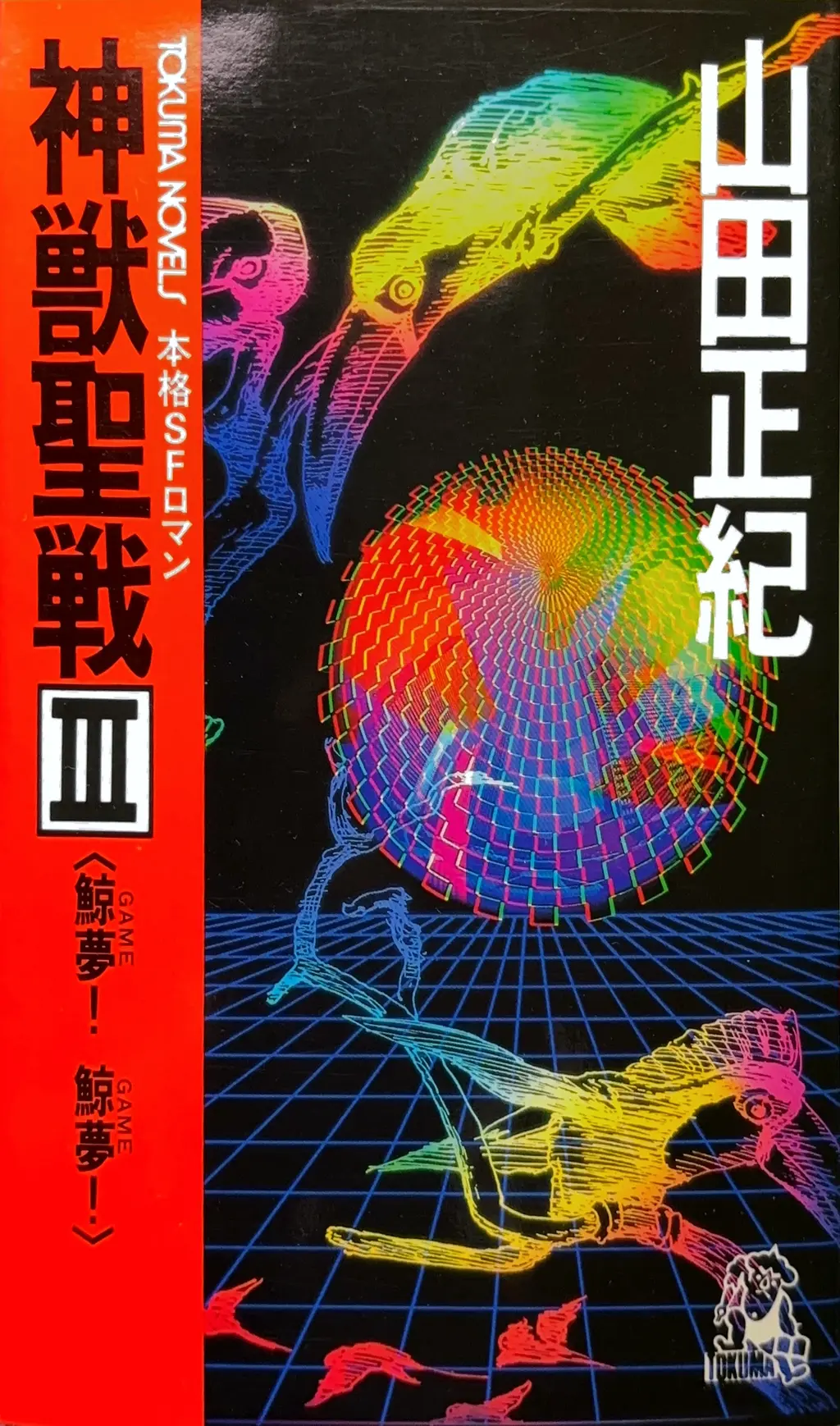
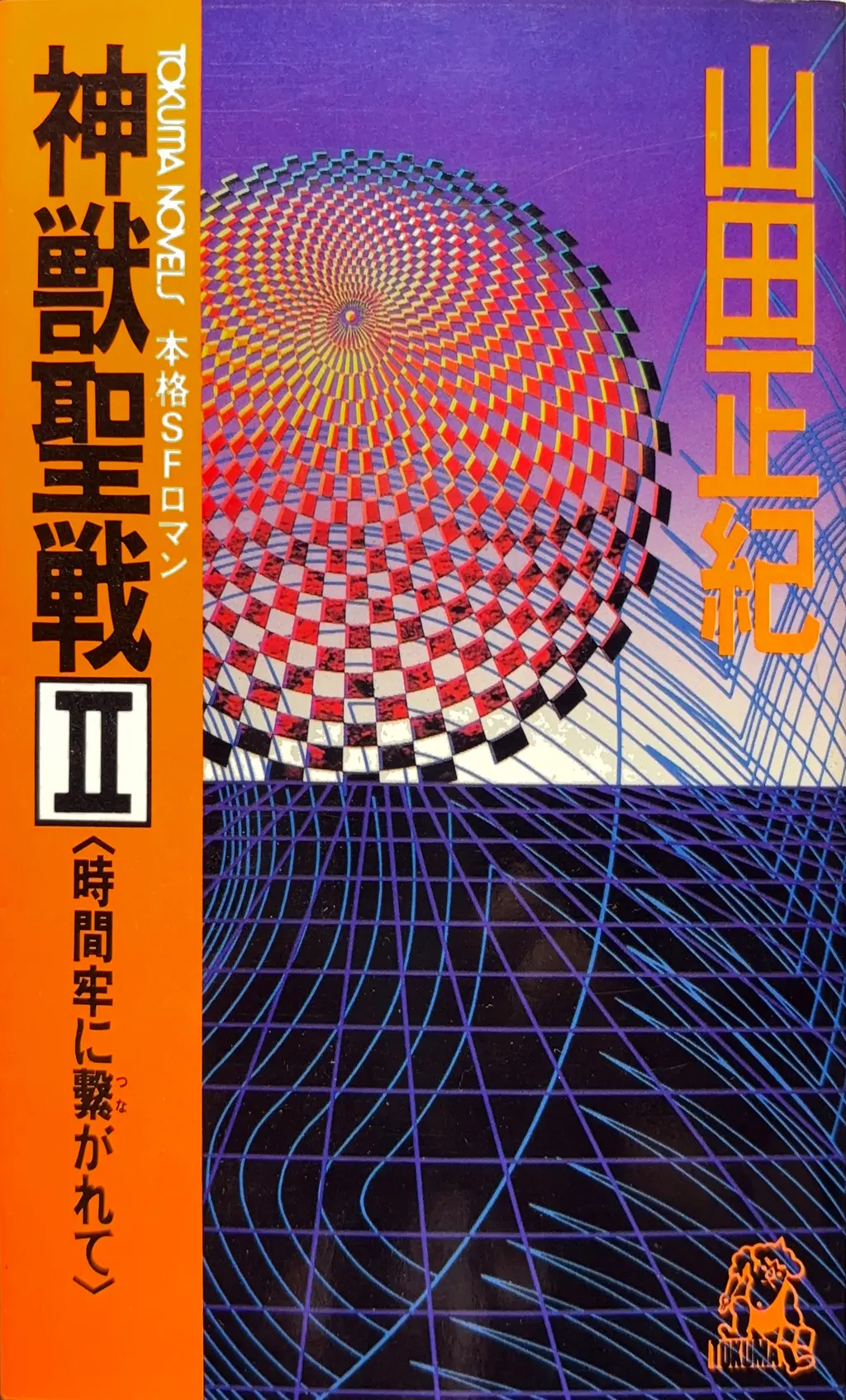


![妖鳥[ハルピュイア]](https://phantomoon.com/wp-content/uploads/2025/03/harpyia-1-1024x1678.webp)