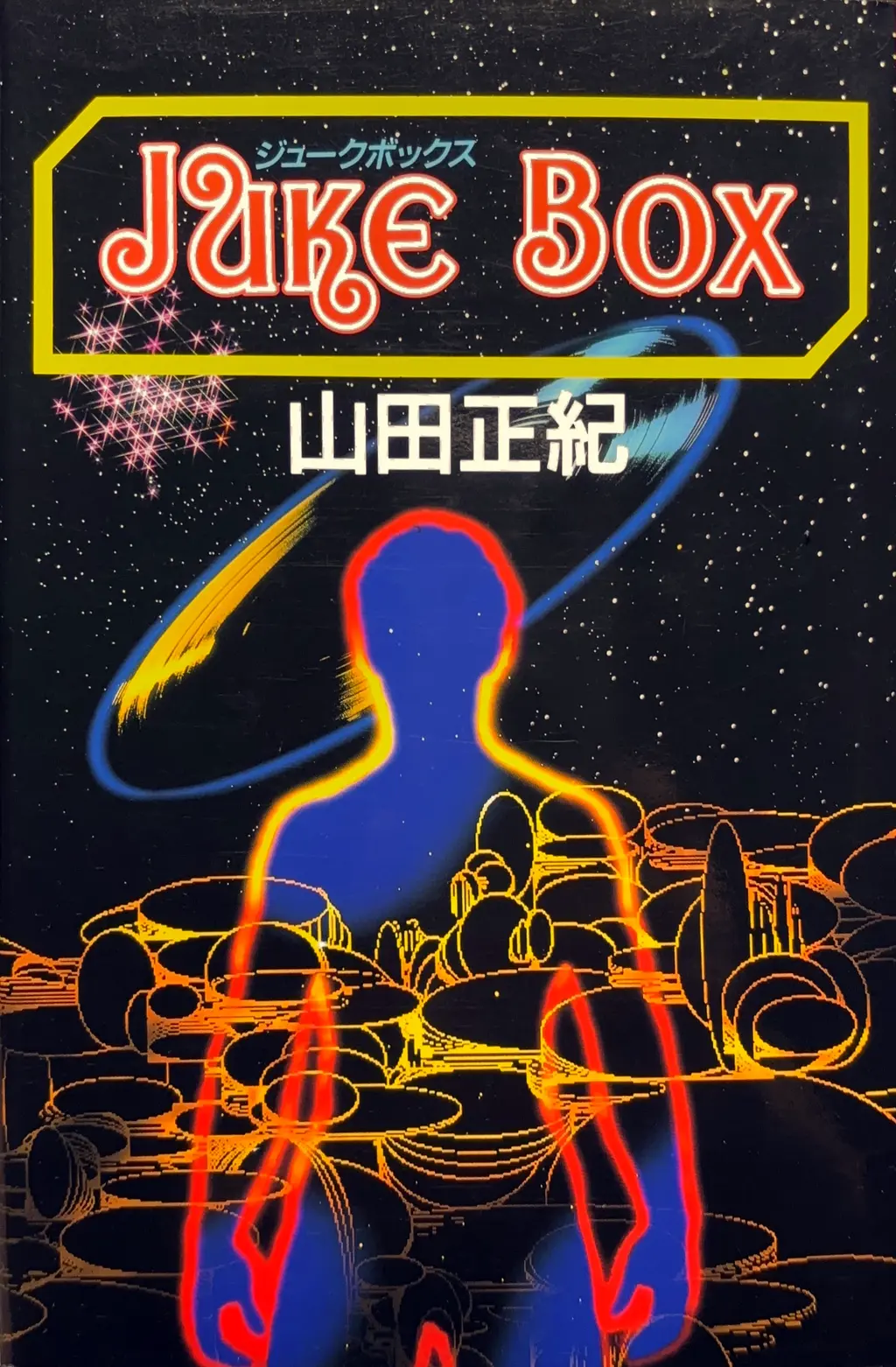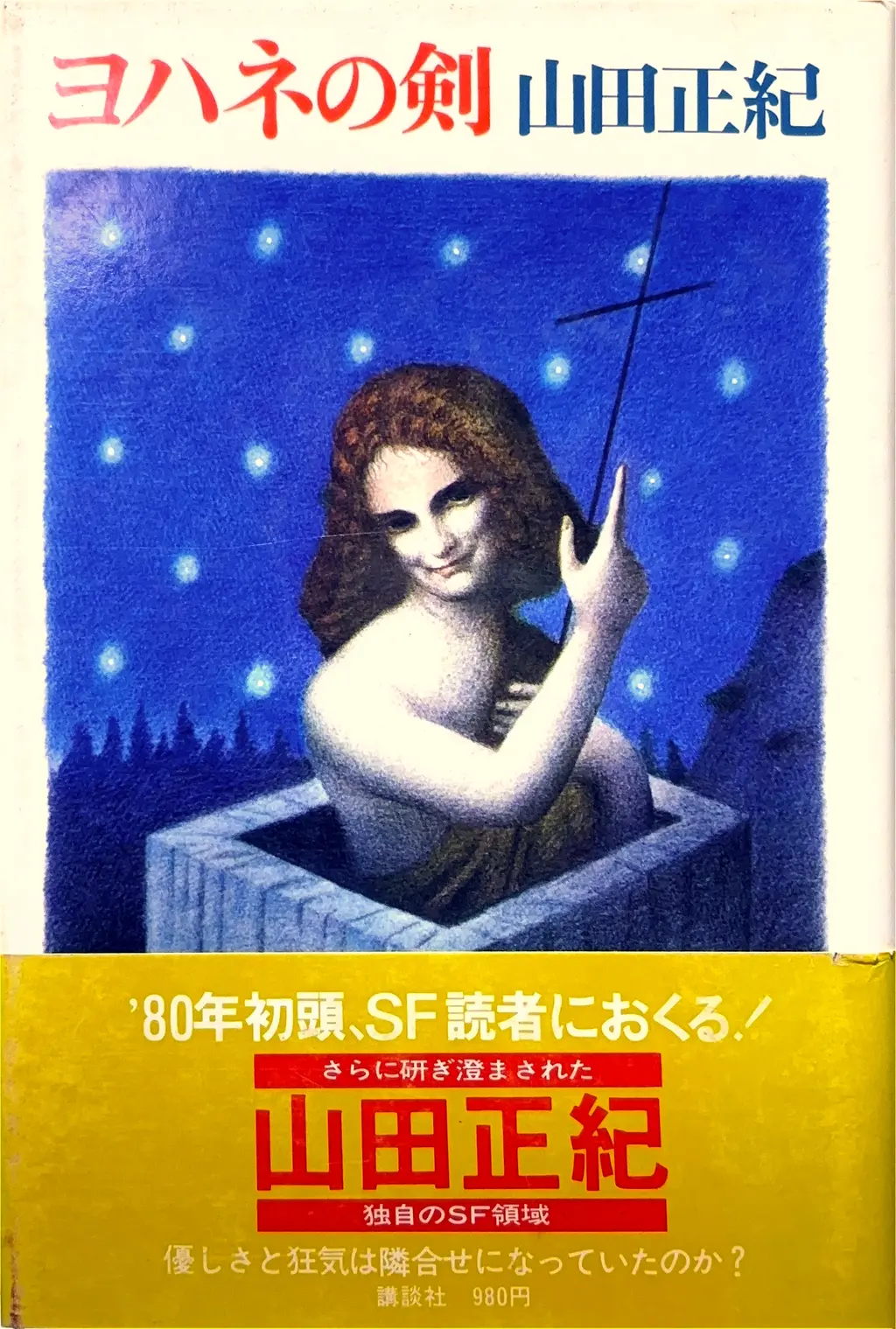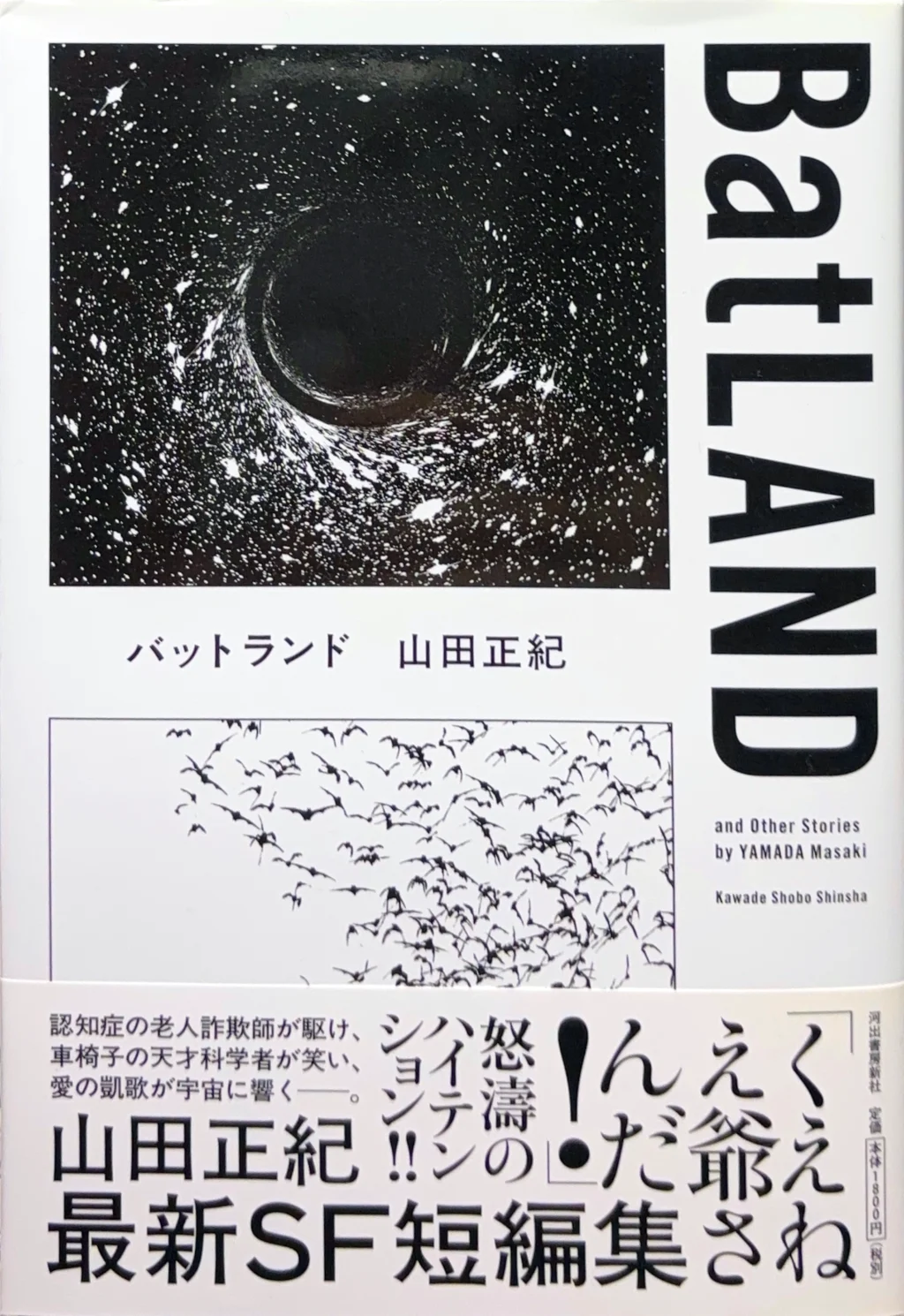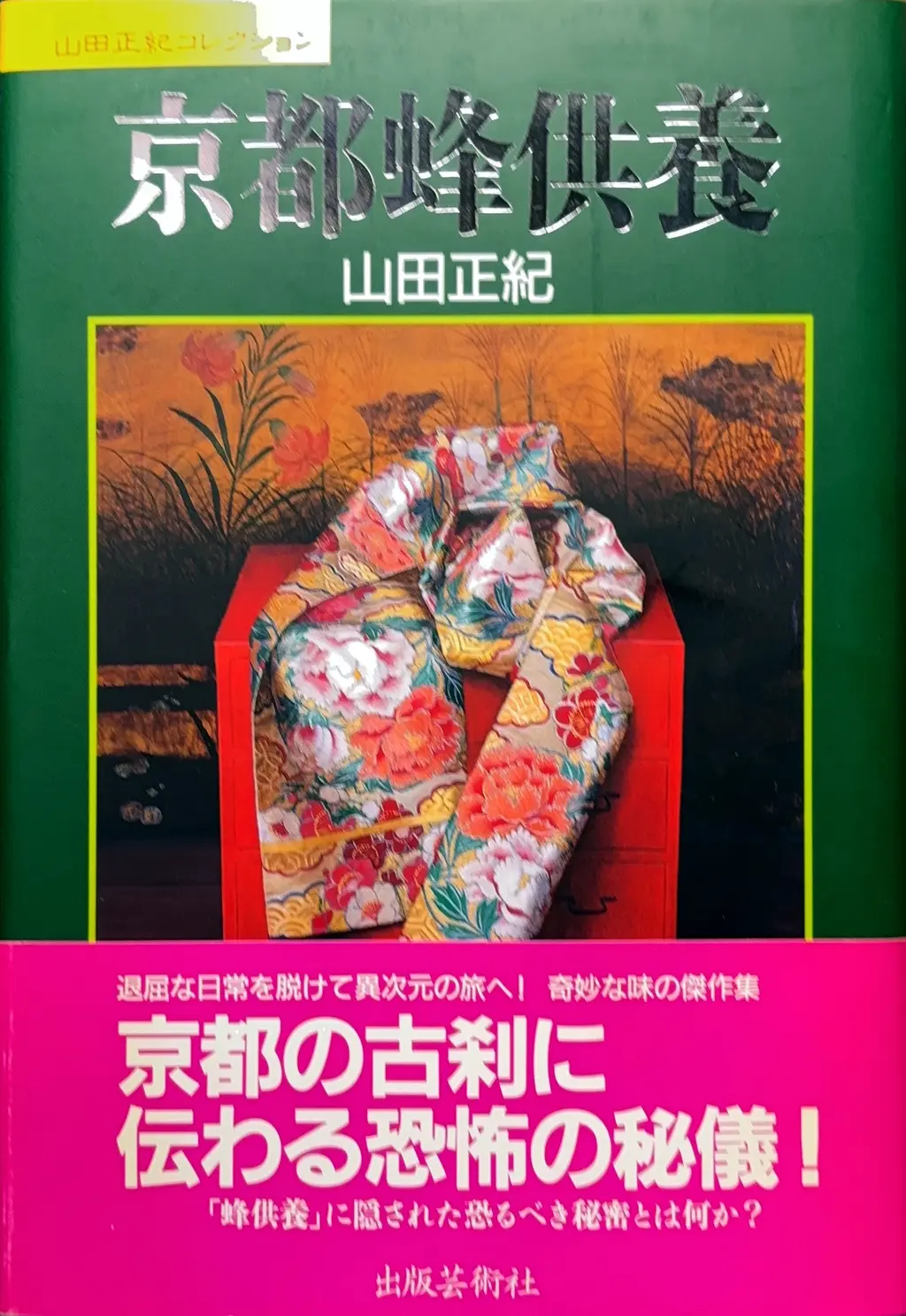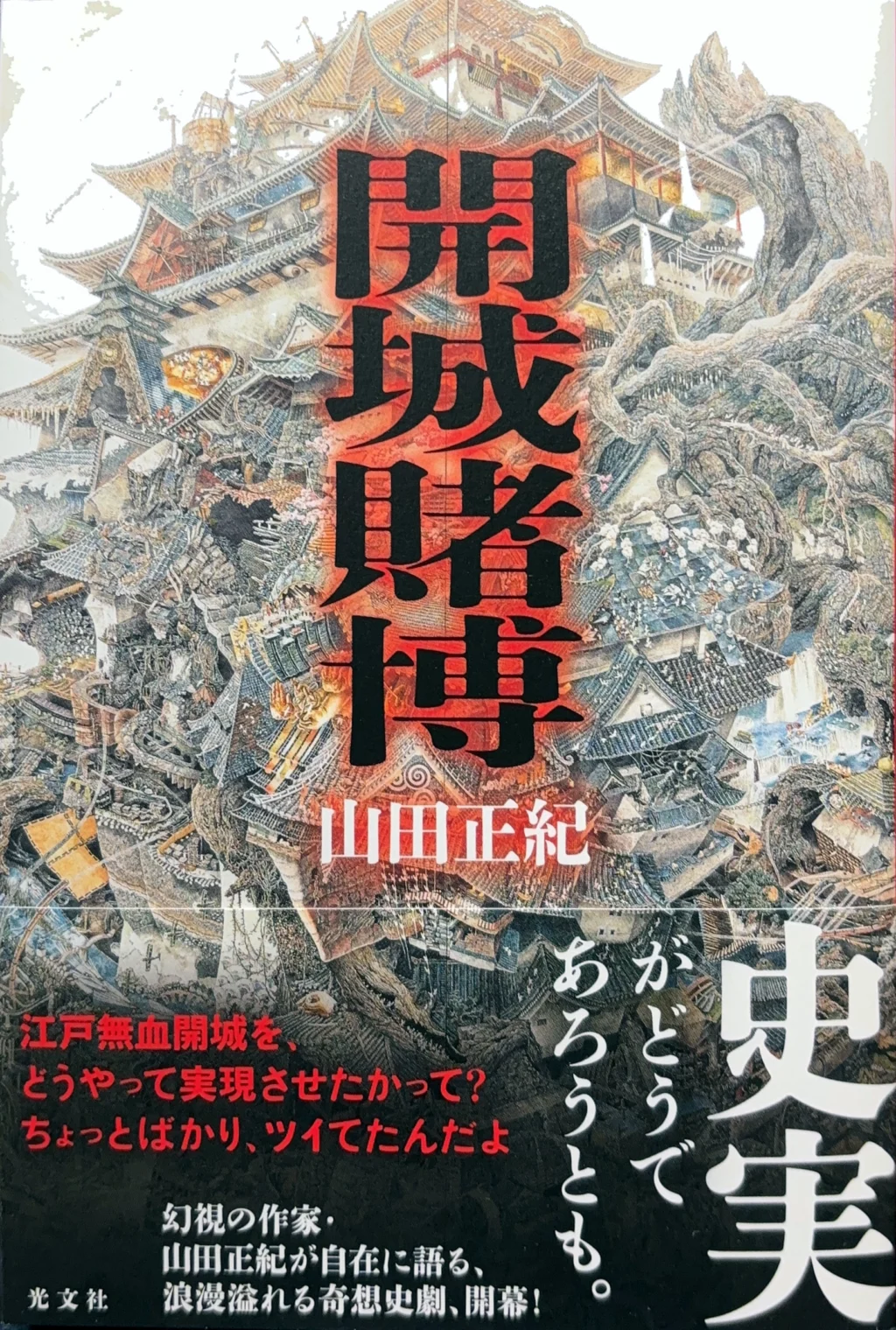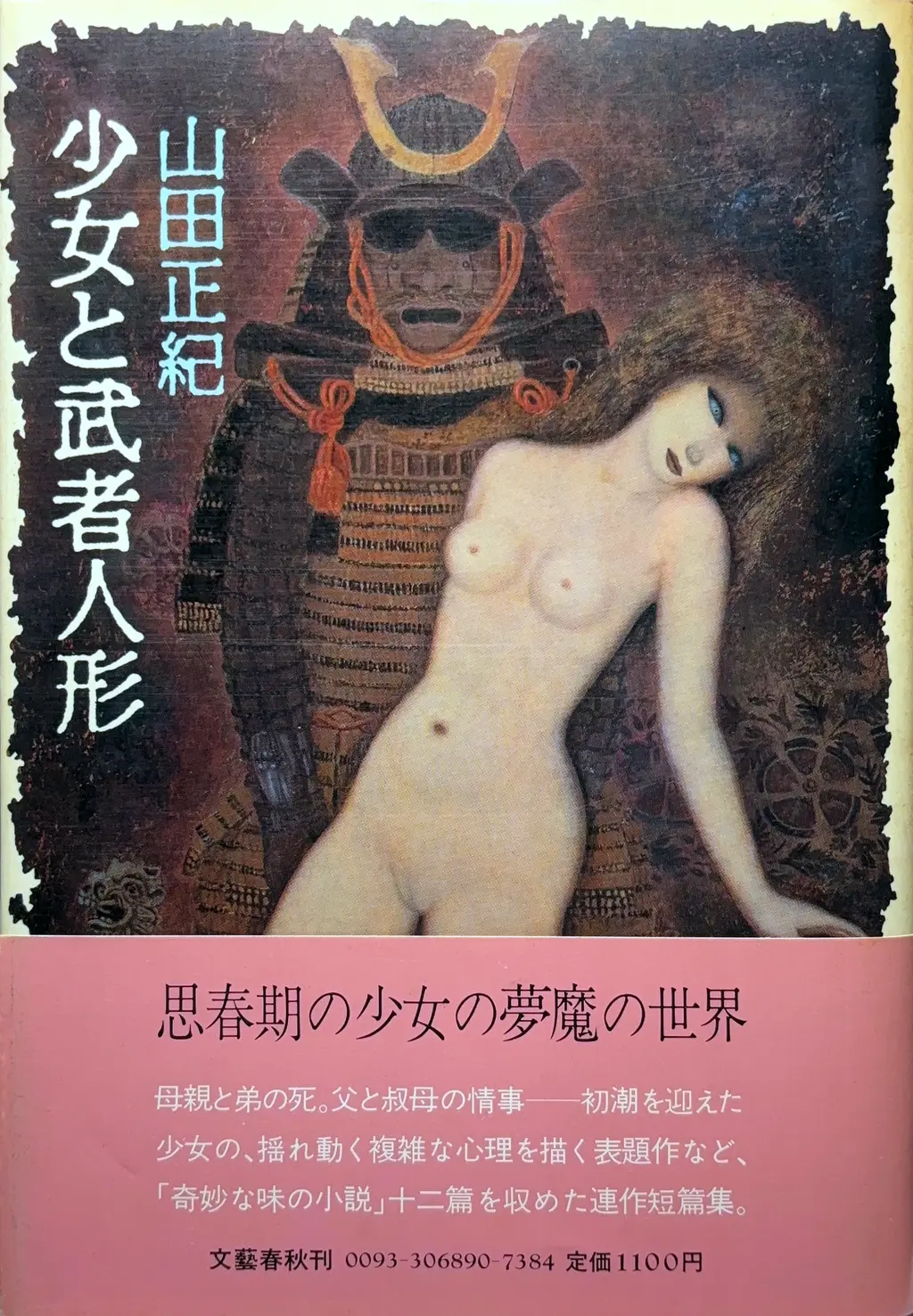| 叢書 | 竹書房文庫(日下三蔵・編) |
|---|---|
| 出版社 | 竹書房 |
| 発行日 | 2021/06/25 |
| 装幀 | Adam Martinakis, 坂野公一 |
収録作品
- 【SIDE A:恐怖と幻想】
- 溺れた金魚
- 夢はやぶれて(あるリストラの記録より)
- トワイライト・ジャズ・バンド
- 逃げようとして
- エスケープ フロム ア クラスルーム
- TEN SECONDS
- 【SIDE B:科学と冒険】
- わが病、癒えることなく
- 一匹の奇妙な獣
- 冒険狂時代
- メタロジカル・バーガー
- フェイス・ゼロ
- 火星のコッペリア
- 魔神ガロン 神に見捨てられた夜
内容紹介
🌀幻想と科学が混ざり合う、異色短編集の深層へ
「ジャンルの壁を越える」といった表現を用いるとき、私は慎重になります。しかし、山田正紀の短編集『フェイス・ゼロ』においては、その言葉がむしろ控えめに感じられるのです。
この作品集は、日下三蔵の編纂による〈竹書房文庫〉の一冊として2021年に刊行されました。全13篇から成るこの短編集は、【SIDE A=幻想とホラー】【SIDE B=SFと実験的ミステリ】という二面性をもった構成で、まるで“顔”を表裏反転させたような構造。
では本記事ではその個別作品に言及しつつ、この短編集がもつ文学的価値、そして山田正紀作品としての位置づけをじっくり紐解いていきます。
🔎『フェイス・ゼロ』が異色たる理由
「短編集でありながら、構成が実験的」
ほとんどの短編集が作品の配列にあまり意味をもたないのに対し、『フェイス・ゼロ』ではSIDE AとSIDE Bで明確な世界観の転換がある。SIDE Aは幻想文学的な短編が並び、SIDE BはSF的、あるいは実験的構造を採った物語群。
この並列性によって、読者は一冊の中で異なる“読む姿勢”を求められるのです。言い換えるなら、「読み手のモード切替」を強要する構成。
SIDE Aでは「不穏と混乱」に身を委ね、
SIDE Bでは「知的好奇心と驚き」に没頭する。
以下、各収録作品の概要です。
【SIDE A:恐怖と幻想】
①「溺れた金魚」
テーマ:死と記憶、錯綜する現実
雨と魚、記憶と死。読者の視界を曇らせるような物語。
ソラリス的と形容されるのも納得。語りのトーンが一貫して湿っぽく、どこか夢の中のよう。死者の記憶が雨に混ざって降り注ぐような詩的イメージが印象的です。幻想と狂気のはざまをたゆたう、山田流ホラー。
②「夢はやぶれて(あるリストラの記録より)」
テーマ:社会崩壊とアイデンティティの揺らぎ
語り手の視点が揺れ、読者の感覚も迷子になる。
冒頭の「これはあなたの夢なのだ」から、既に読者は混乱の海に放り込まれる。グロテスクな妄想、意識の飛躍、語りの混濁——どこか漫画的な狂気。語り手が本当に“語り手”なのかすら不確かという、メタ的な視点が仕掛けられています。
③「トワイライト・ジャズ・バンド」
テーマ:音楽と記憶、幻影としての過去
ジャズの音色に導かれ、過去と現在が混じり合う。
かつてのバンド仲間との邂逅を描くノスタルジックな一編。音楽を媒介にして“かつて存在したかもしれない時間”が浮かび上がる構造は、幽霊譚にも似た後味を残します。トワイライト・ゾーン的な雰囲気。
④「逃げようとして」
テーマ:逃走願望と現実逃避
「逃げる」ことに意味はあるのか? 読む者の価値観が問われる。
曰くありの宿に逃げ込んだ男が体験する奇妙な出来事。『ねじまき鳥クロニクル』的というか、現実からの逃避がまるで永遠の罠のように展開していきます。物語のループ感が不気味でクセになる。
⑤「エスケープ フロム ア クラスルーム」
テーマ:現実と幻想の交錯
不登校児の見た世界は、妄想か、救いか。
学校という閉鎖空間を舞台に、幻想的逃走劇が展開される。子どもが感じる現実の重さと、それを脱するための“想像”の力がストレートに描かれていて、どこか痛ましい。夢の世界に逃げ込むことでしか生きられない人々の悲しさがにじむ。
⑥「TEN SECONDS」
テーマ:時間・意識の濃縮実験
十秒間でどれだけの物語が描けるのか。
実験的作品。意識が交錯し、同時に存在する記憶や感情が読者に“襲いかかって”くる。時間の感覚が崩れるような読書体験を味わえます。まるで時間を“見る”ことができるような錯覚。
【SIDE B:科学と冒険】
⑦「わが病、癒えることなく」
テーマ:過去・存在・時間の哲学
過去に戻りたい人々の最後の希望は、哲学的絶望に変わる。
タイムスリップという古典SFのテーマをベースに、極めて人間臭く、しかし知的に展開される作品。ヴィトゲンシュタインの哲学を応用し、「過去に戻っても過去の自分には会えない」というロジックが示される。
⑧「一匹の奇妙な獣」
テーマ:言語と存在、そして失敗
カフカ的で実験的。でも完成度は……。
山田正紀自身が「失敗作」と認めた作品。言語哲学(プラハ・ドイツ語)を軸に構成された非常にマニアックな短編。構想は壮大だが、短編という枠組みには収まりきらなかった感。むしろ長編で読んでみたかった。
⑨「冒険狂時代」
テーマ:虚構と現実の境界、スラップスティックな批評
保険とスタントマンの話が、なぜかシュールに交錯する。
1978年発表の古めの作品で、懐かしき“SFショートショート”の香りが漂う。シニカルでユーモラス、でもどこか皮肉。筒井康隆やかんべむさしの影響を感じるような軽やかな毒気があります。
⑩「メタロジカル・バーガー」
テーマ:合理化社会と人間性の喪失
マニュアルが世界を支配したら、最後に残るのは何か?
マクドナルド的ファストフード文化をモチーフにしたブラックな風刺。極限まで自動化・最適化されたサービスが、やがて“人間であること”を抹消するという近未来的恐怖。安部公房『人間そっくり』に通じる怖さがあります。
⑪「フェイス・ゼロ」
テーマ:表情と感情、ロボットと伝統の衝突
文楽×ロボティクス=破壊のSFミステリ
無表情のカシラ=フェイス・ゼロが生み出す精神的崩壊と、そこに絡む殺人事件。表情工学という実在の学術分野と伝統芸能が交差する、まさに“現代日本SF”の真骨頂。ミステリとしての構造も巧妙で、読後に「うまい!」と唸らされる傑作。
⑫「火星のコッペリア」
テーマ:アンドロイドと人間の境界、記憶の再構築
真相が暴かれる構成は、叙述トリック的快感。
火星から地球へ帰る宇宙船で起こる密室的ミステリ。タイトルの“コッペリア”は人形の代名詞。読者の推理をあざ笑うような反転劇で、巧緻な語りの構成が際立つ。アンドロイドは人間とどこで違うのか?という問いが響く。
⑬「魔神ガロン 神に見捨てられた夜」
テーマ:神話と機械、オマージュと越境
手塚治虫の影が、山田正紀の文体で蘇る。
手塚原作を山田が小説化した特異な作品。原作未読でも楽しめるが、知っていればより深く味わえる仕掛けあり。神と機械、正義と破壊、あらゆる対立が物語の中で交錯し、最後は幻想へと昇華していく。
🎯山田正紀作品としての意義
山田正紀はデビュー作『神狩り』以来、常に“認識とは何か”“言語と存在の関係”といった哲学的問題を問い続けてきた作家です。本作でもその問題意識は健在であり、「自己」と「他者」の認識境界を壊すような物語構成が随所に見られます。
『フェイス・ゼロ』の中では、表現媒体が小説であることを逆手に取ったような手法が目立ち、「語り手=現実ではない」構造が多用されている。それが故に、読者は終始「今、自分はどこにいるのか?」という不安を抱き続けるのです。
🧠ラストにひとこと
ジャンル、語り、構造、思想。
あらゆるレベルで挑戦的なこの短編集は、「物語とは何か?」という根本を読者に問いかけてきます。
たった数十ページで、現実が歪むような体験をくれる――それが山田正紀の短編の力。
『フェイス・ゼロ』は、その魅力が凝縮された一冊です。
 不安と月
不安と月