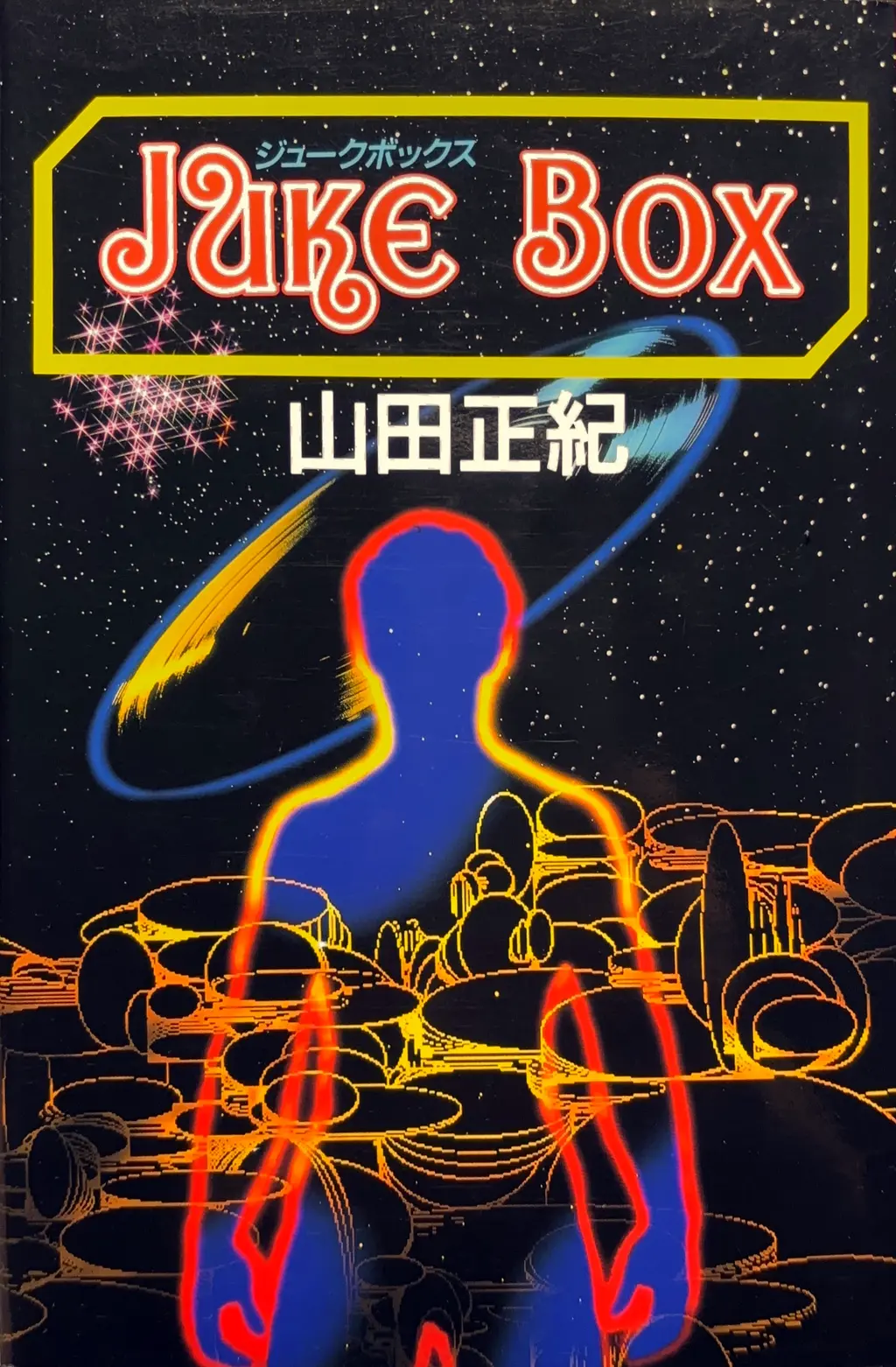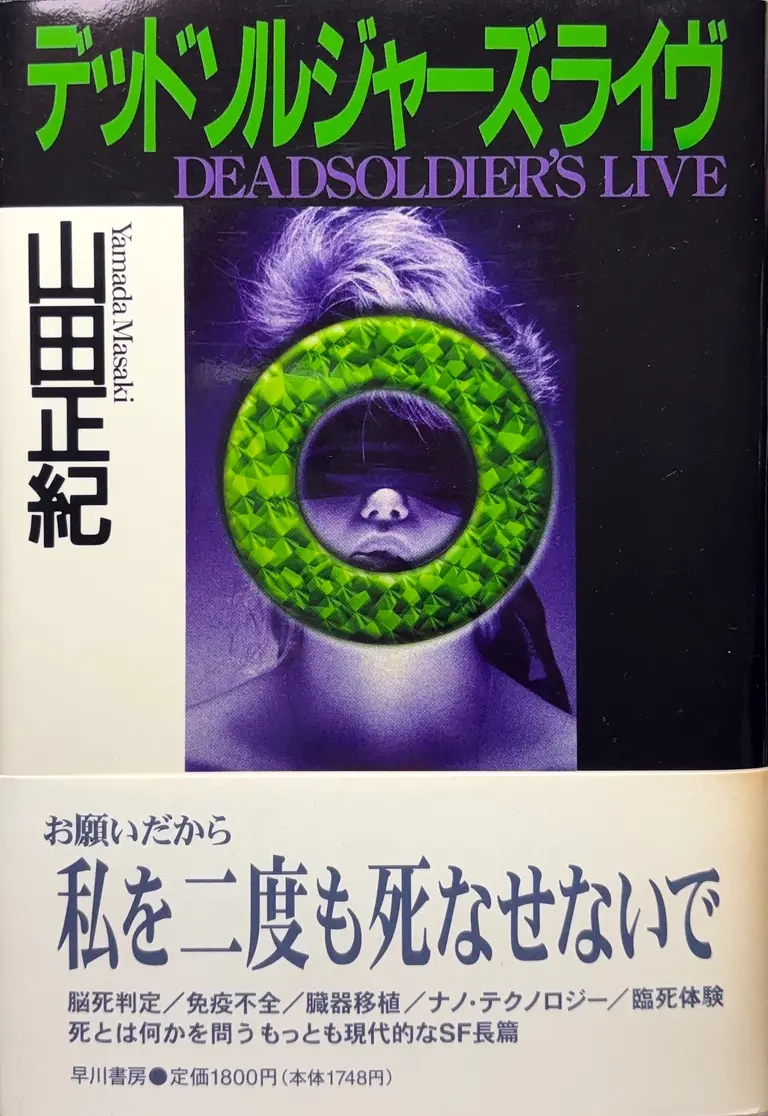
| 叢書 | 初版 |
|---|---|
| 出版社 | 早川書房 |
| 発行日 | 1996/11/30 |
| 装幀 | 辰巳四郎、本田晋一 |
収録作品
- 監視塔――〈否認〉
- 薔薇のいれずみ――〈怒り〉
- 偽りの微笑――〈怒り〉
- 爬虫類――〈怒り〉
- もうひとりの私――〈取り引き〉
- 六本木純情派――〈抑鬱〉
- サトウキビ――〈抑鬱〉
- 監視塔――〈受容〉
内容紹介
『デッドソルジャーズ・ライヴ』とは?
山田正紀の『デッドソルジャーズ・ライヴ』は、死をテーマにしたSF連作短編集だ。本作はキュブラー・ロスの「死の受容プロセス」(否認・怒り・取り引き・抑鬱・受容)に沿う形で構成され、各短編が異なる視点から「死とは何か?」を問うている。
死とは、単なる肉体の消滅なのか。それとも、意識がなくなることなのか? あるいは、死んだ者が生きている者の記憶の中で存在し続ける限り、本当の死は訪れないのか? 本作は、そんな哲学的な問いを、ナノマシンや脳死判定装置といったSF的ガジェットを駆使して描き出している。
以下、各短編について紹介しよう。
各短編の紹介
「final episode part1 監視塔」――〈否認〉
主人公・柚子尚美は、原因不明の病に冒されていた。彼女の夫・欧馬は、自身の免疫疾患が尚美のせいだと主張する。やがて尚美は脳死状態に陥り、脳死判定装置〈意識共鳴スペクトローラー〉にかけられるが、装置は彼女を「脳死」と判定できなかった。
死んでいるのか? それともまだ生きているのか?――この物語は、科学技術が「死」の概念を揺るがす世界の幕開けとなる。
「episode1 薔薇のいれずみ」――〈怒り〉
東京・晴海で開催されるVR見本市。主人公はヘッド・マウント・ディスプレイを装着するが、そこで見たのは、プログラムとは無関係の光景だった。薔薇のいれずみを持つ女とともに機関車に押し込まれ、どこかへ運ばれる自分。そして現実世界で彼が出会ったのは、霊柩車に追われる若い女――彼女の肩には、あの「薔薇のいれずみ」があった……。
「episode2 偽りの微笑」――〈怒り〉
大学の哲学科でエロティシズムの研究をする「ぼく」。助手の水島が持ち込んだビデオには、謎の女「這う女」が映っていた。彼女は、男に想像を絶する快楽を与え、その代償として死をもたらす存在だという。
この女は何者なのか? そして、彼女に取り憑かれた男の運命は? エロスとタナトスの境界線が揺らぐ、不気味な一篇。
「episode3 爬虫類」――〈怒り〉
死をもたらす女たち「レプタイル」を狩る組織「イレイザー」。そのトップが、よりによってレプタイルの虜になってしまったという。その相手は、主人公にとっても馴染みのレプタイル、ナオミだった……。
人間とは、死を恐れながらも、死に惹かれる生き物なのかもしれない。
「episode4 もうひとりの私」――〈取り引き〉
不倫相手の燵彦とともに事故に遭った「わたし」。燵彦は死に、「わたし」が妊娠していたはずの子供は消えてしまった。
死者との境界を超え、消えた子供を求める「わたし」は、病院を彷徨う。だが、彼女が目にしたものは……。
「episode5 六本木純情派」――〈抑鬱〉
自己免疫病を患う「私」は、六本木で見かけた少女に惹かれ、彼女を追い求めて街を彷徨う。しかし、自らの手首には「死を検知する装置」デスピュレータが装着されていた。少女を追うことは、「死」に向かうことと同義なのか?
「episode6 サトウキビ」――〈抑鬱〉
ドブ川に浮かぶ男が握りしめていた広告ティッシュ。それはファッションヘルス〈SUGARCANE〉のものだった。
男は〈SUGARCANE〉を求め、街を彷徨う。死に瀕した者が最後にすがるものは、幻か、それとも現実か?
「final episode part2 監視塔」――〈受容〉
マングローブ林にそびえる監視塔。そこには、三人の男女が眠り続けていた。
番号で呼ばれる彼らは、一体何者なのか? そして、この塔が象徴するものとは?
物語は、死の先にある「何か」を提示しながら幕を閉じる。
『デッドソルジャーズ・ライヴ』を読み解く
『デッドソルジャーズ・ライヴ』は、単なる「脳死SF」ではない。物語を貫くのは、「死とは何か?」という根源的な問いである。
また、本作は単なる短編集でもなく、各エピソードが互いに呼応しながら、読者に「死の受容プロセス」を追体験させる構成となっている。この実験的手法こそが、本作を唯一無二の作品にしている。
さらに、作中には洋楽への言及も多く、「ライヴ」という単語が持つ「ミュージシャンのライブ」という意味合いもある。死とは、終焉ではなく「演奏が続くこと」なのかもしれない。
山田正紀の筆致は、幻想的でありながらも、現実の科学技術や哲学的思索と強く結びついている。本作は、哲学とSF、エロスとタナトス、科学とオカルトが交錯する、唯一無二の傑作といえる。
 不安と月
不安と月